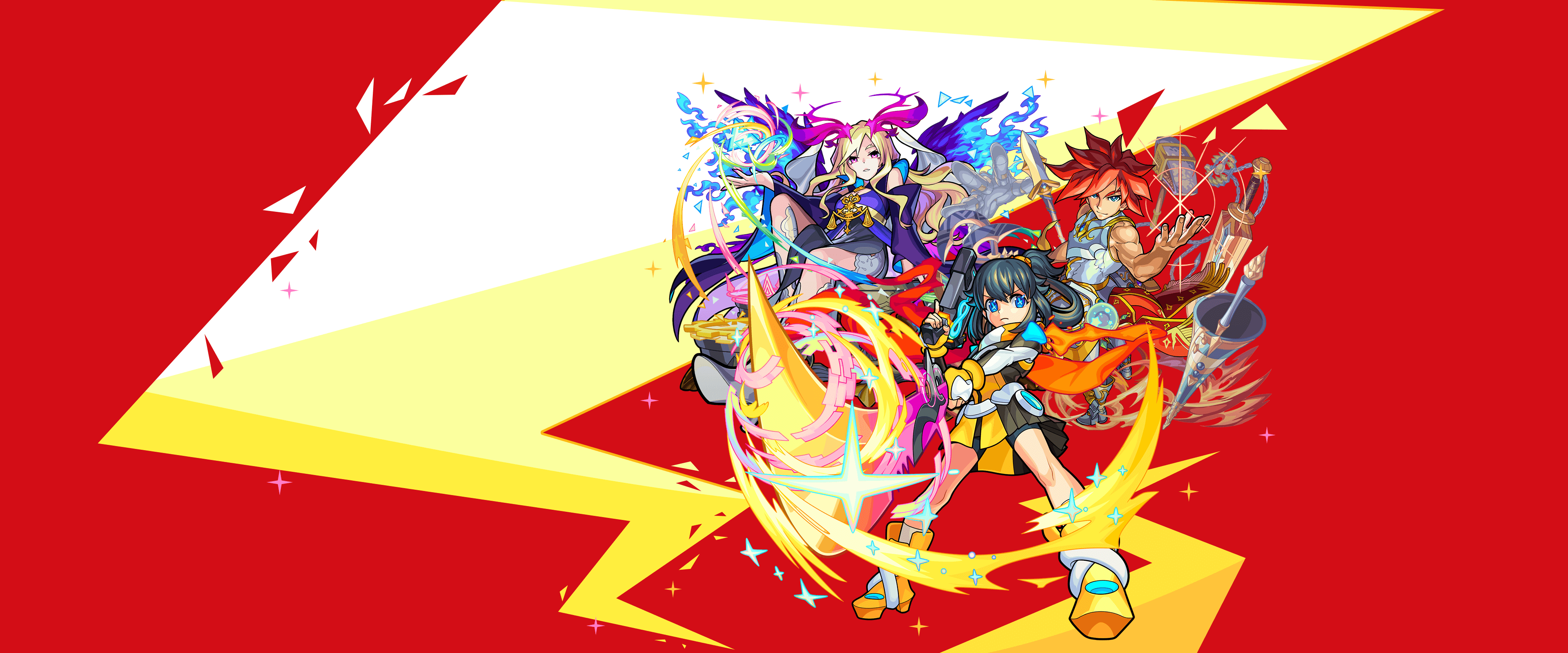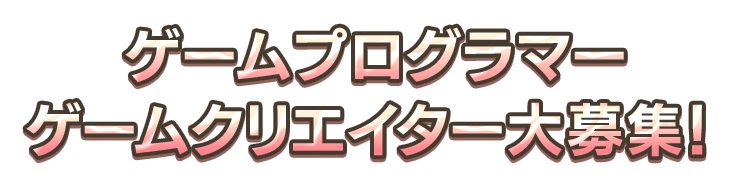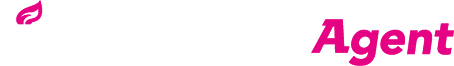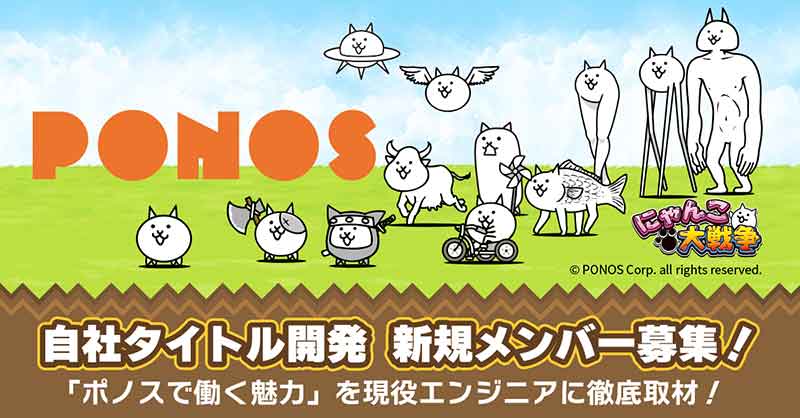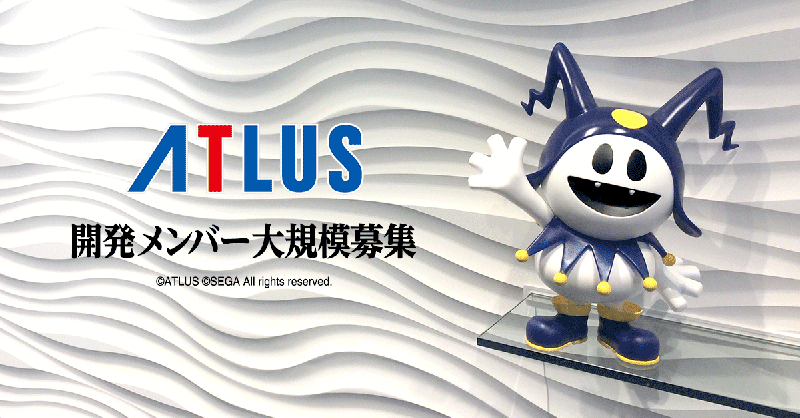ミクシィ ゲーム開発エンジニア取材特集

ミクシィはSNSやスポーツ、メディアなど、多角的な事業を展開しています。
なかでも、デジタルエンターテインメント事業では、世界累計利用者数5600万人(2021年10月時点)を突破した「モンスターストライク」や「共闘ことばRPG コトダマン」などのスマホゲームの開発・運営を行いつつ、先日クローズドβテストを実施した「モンスターストライク ゴーストスクランブル」をはじめとした新規IPタイトル「モンストシリーズ」の創出にも力を入れています。
今回は、国内外から多くの支持を集める「モンスト」を開発する株式会社ミクシィのエンジニアマネージャーとサーバエンジニア、「モンストシリーズ」のエンジニアに、ミクシィならではのゲーム開発やミクシィでのエンジニアの働き方について話を伺いました。
「モンスト」開発エンジニアマネージャーが語るミクシィが求めるエンジニアとは?
国内外から多くの支持を集める株式会社ミクシィの「モンスト」。スマホゲームの最高峰を開発するクライアントエンジニアをマネージャーとして率いる岡本氏に、ミクシィで働くエンジニアの特徴や求められる能力、ロングヒットタイトルに関わったことで得られたものについて伺いました。
ミクシィだから、「モンスト」だから、実現可能なことがある
――はじめに、ゲームクリエイターを目指したきっかけを教えてください。
岡本
子供の頃に「大乱闘スマッシュブラザーズ」を家族や友人と遊んでいてめちゃくちゃ楽しいなと感じたんですよね。そして、世界大会などを見て海外の人も同じように興奮して楽しんでいるのも知りました。その時からゲームは言葉の壁を超え世界中の人と楽しめるものだと感じ、将来はゲームのエンジニアになって、「自分が受けた感動や興奮を世界中の人に届けたい」という思いを抱いたことを覚えています。

写真:株式会社ミクシィ 岡本 勇太さん
――多くのゲーム会社がある中から、ミクシィに入社した理由を教えてください。
岡本
-
根底には「友達とゲームを遊んだときに感じた盛り上がり」を届けたいということがありました。就職活動で参加した採用イベントで、「ミクシィはコミュニケーションを軸にしたみんなでわいわいできるゲームを作っている会社」という話を聞き、ここであれば作りたいゲームを実現できると感じました。
――ミクシィに入社後、エンジニアとして印象的だったことはありますか?
岡本
やはり、実際に作ったものを「多くの人に遊んでもらえる」ことですね。自身の携わった機能に対して、リリース直後に多くのユーザーさんの評価がいただけるのはエンジニアとしてとてもうれしいです。良くも悪くも自身の反省や次に繋げる機会になるため、もっと良いものにしたいと思えます。
また、一人のプレイヤーとして、ゲームをプレイする上で気になった部分についても、エンジニアからも気軽に改善案を出して、プランナーやデザイナーと考えて進められる文化があります。
なかには、ゲームの内部を熟知しているクライアントエンジニアだからこそ提案できたストライクショットや友情コンボなどもあります。「モンスト」をおもしろくする要素を自分の手で実装できることは、ここでしか得られない体験ですね。
超巨大タイトル「モンスト」ならではのやりがいと難しさ
――開発において、「モンスト」と他のゲームで異なる点はありますか?
岡本
-
昨今のゲーム開発環境では、Unityが大きなウエイトを占めるようになっていますが、「モンスト」はCocos2d-xを採用しています。Cocos2d-xは、「モンスト」開発当時に主流だったフレームワークです。UIなどデザインの実装とコード(プログラム)が密接につながっていて、クライアントエンジニアがデザイナーと連携して、「コード単位で細かい調整」を必要とする点が、Unityを使った開発と大きく異なるポイントです。UnityではPrefabやTimelineなどが備わっているため、ある程度他職種の作業もUnity上で完結できますが、「モンスト」ではCocosBuilderといった専用のアプリケーションなどを使用します。
――長く続いているタイトルならではの特徴はどんなところでしょうか?
岡本
-
「モンスト」の開発現場には、8年以上の長期運用実績で培われたものがとても多いです。経験したことのないレベルの障害やさまざまな課題への対応、細かいレベルの調整を間近で見られる…。実際に手を動かす体験を通じて得るものは、非常に大きいと感じました。
また、「同じことをユーザーに届ける」だけでなく、「次はどういうことをしよう」「新しい体験をどう届けよう」と、常に考えている現場でもあります。ゲームをより良くすることを、職種に関係なく全員が考えている。そうして生まれたアイディアをすぐに実装できることも、クライアントエンジニアにとって大きなやりがいになっています。
一方で、長く続いているため、すべての実装や仕様を把握することが難しいことは、開発効率を上げていくためにも考えないといけない課題になっています。実装したエンジニアが退職していて、よりコアな実装理由などがわからないケースもあって、今後5年10年と運営していくためにも、「暗黙知」を「形式知」にしていくことはとても重要です。
――ミクシィのクライアントエンジニアとして働く魅力は何ですか?
岡本
「モンスト」は、プレイヤーが「身近な人とマルチプレイをする楽しさ」を重視しています。コロナ禍で、対面で遊ぶことは難しくなったりもしていますが、だからこそ常に「コミュニケーションを大事にする」姿勢を持って新しい機能の追加などの開発をしています。そうした文化を持つ人たちと働けることは大きな魅力であると思います。
また、ミクシィは意思決定の軸として「ユーザーサプライズファースト」を掲げていますが、これはユーザーのことを大切に考えていないと実現できないものです。「ユーザーにどういう価値を届けたいのか?」ということが重要なので、ゲームの新しい機能を考えたときは、真っ先にそのことが問われます。
ゲームを開発するとき、メンバーがみんな同じ方向を目指している状態を作ることは難しいものですが、こういった軸 があることでミクシィでは自然と成り立っていると感じます。やりたいことに対するギャップがないので、とても仕事がしやすいことは大きいですね。
「モンスト」クライアントグループ、ミクシィが求めるエンジニアとは
――「モンスト」クライアントグループが求めるエンジニアについて教えてください。
岡本
「モンスト」のチームには2名のマネージャーがおり、全体で23名のエンジニアで構成されています。現在私のグループに所属しているエンジニアは7名です。
私のグループに配属されるエンジニアに求めるものは、案件(課題)をリードしつつ、実際に手を動かして実装もできること。つまり、異なることを同時に推進できる人材を求めています。言われたとおりに実装するだけでなく、内容に対して自分の意見を発信できることも重要です。
ほかには、「これまでの開発現場で、いかにプランナーやデザイナーと関わってきたか」という部分を重視しています。「モンスト」の開発において、他職種の人とのコミュニケーションを取って進めることは必須なので、対話の経験が少ない、あるいは苦手という人には、やりたいこととのギャップが生じてしまいます。技術があることはもちろんですが、コミュニケーションに対して積極的な人を求めていきたいと考えています。
――ミクシィにマッチするエンジニアはどんな人でしょうか?
岡本
「こういうサービスを作りたい」というエンジニア気質の人より、「このユーザーに届けたい」「友達と楽しめるものを作りたい」というように、サービスの先にあるユーザーを考えられる人が向いていると思います。
ミクシィでは、エンジニアという枠にとらわれず俯瞰的に物事を見ることが要求されるので、ただ実装するだけでなく、その機能に対して意見を言える必要があります。ただ、自分の意見に固執しているだけでは、ほかのメンバーとうまくいかないことがあるかもしれません。
――岡本さんは、少し変わった経緯でマネージャーに就任されたと伺いました。
岡本
-
2021年3月にリーダー就任の打診があり、入社してちょうど4年目を迎えるタイミングでしたので、「今までと同じことをしているだけでは良くない」という意識もあって引き受けました。
ところが、その2週間後くらいにマネージャー就任という話になりまして…。4月はリーダー業務、5月からはマネージャー業務を務めています。「新しいチャレンジをしないといけない」という思いはありましたが、心の準備はまったくできていない状態でした。
――マネジメントする立場になって、お仕事の内容や意識の変化はありましたか?
岡本
-
「モンスト」の開発全体への貢献を考え、それをいかに実行していくかが問われるようになりました。エンジニアとしては、「レガシーな部分の改善」や「新技術の導入」などを考えていくかたちですね。
実装に携わることもありますが、メンバーのサポートや他部署とのコミュニケーションを円滑に行う役割をおもに担っています。
また、マネジメントする立場になり、メンバーと対話をしていく中で、「ほかのメンバーとのギャップ」「自身が貢献できる内容」といった悩みに対しては、自分が同じ立場だったときのことを思い出して一緒に解決するようにしています。
というのも、私自身、前任のマネージャーが多くのチャンスを与えてくれていて、それが私の成長につながっていたことにも気付かされました。同様に私自身もチャンスを作れるようにしていければと今では考えています。
ミクシィで描けるエンジニアのキャリアプランとは

――ミクシィでは、どのようなキャリアを目指せるのでしょうか?
岡本
-
マネージャーとしてチームを率いる立場を目指すこともできますし、エンジニアとして技術を追求するスペシャリストに進むことも可能です。仕事を進めていると必然的に、「自身が目指す方向」を考えるようになりますし、目指す立場に会社が何を求めているかも提示されます。その指針となるのが等級制度です。自律性や推進力など、より成長していくにつれ上の等級に上がり、選択肢も広がっていきます。
――「モンスト」以外のチームで働くこともできますか?
岡本
-
「モンスト」はミクシィのオリジナルIPですから、その中でやりたいことがあるエンジニアには、とてもいい環境だと思います。
一方で、新しいタイトルも常に探っているため、ゼロベースの開発にも携われる会社でもあります。自分の得意な分野に集中することも、タイトル全体にトータルで関わるような働き方も選べます。
――ご自身は今後、どのようなキャリアプランを描いていますか?
岡本
-
根底には、「エンジニアとして成長していきたい」という思いがあります。マネジメントはやりたくないわけではなく、「やってみないとわからないことを経験しておきたい」と考えています。「モンスト」のマネージャーは今しかできない経験で、自分自身の成長につながっていますし、さらに先のキャリアを考えたときに役立つものであると感じています。
――最後に、これから加わる新メンバーへメッセージをお願いします。
岡本
-
エンジニアとしてのスキルを伸ばしたい人にとって、長い歴史と大きなユーザーを抱える「モンスト」は、確実にやりがいのあるタイトルです。また、キャリアアップを目指す場合も、若さなど年齢に関係なくマネジメントに携われる環境でもあります。
私もマネージャーとして、スキルアップを目指す人、マネジメント方面を伸ばしたい人、それぞれのキャリアプランに合わせて多くの機会を作っていきたいと考えています。いっしょに成長していけたらと思いますので、ぜひご応募ください。

-
株式会社ミクシィ
モンスト事業本部 ゲーム運営部 クライアント2グループ 岡本 勇太 - 2018年新卒で株式会社ミクシィに入社し、現在はエンジニアグループのマネージャーとして従事。「モンスターストライク」および「モンスターストライク スタジアム」では、UIやシステム領域の実装をはじめ、人員調整や開発全体課題のハンドリングを行うなど幅広く活躍中。
ミクシィ「モンスト」を支えるサーバーサイドエンジニアインタビュー
圧倒的なユーザー数を誇る「モンスト」には、強固なネットワークとサーバーが欠かせません。特に、オンプレミス(※)と3つのクラウドを並行して使用しているサーバーの運用は、高い技術力を持つサーバーサイドエンジニアなしでは語れないもの。
ミクシィが、どのように大量のトラフィックをさばいているのか、新卒で入社後、一貫してサーバー畑を歩んできた浅野氏に話を伺いました。
※ 自社のサーバーにスマホゲームなどのシステムを組んで運用すること
世界的なスマホゲームを裏から支えるのがサーバーサイドの役割

写真:株式会社ミクシィ 浅野 大我さん
――新卒でミクシィに入社された経緯と現在担当している業務について教えてください。
浅野
-
インフラやネットワークに興味があったので、ゲーム業界を志望していたというより、「サーバーに関わる仕事をしたい」と考えていました。その中で大規模なサーバーを抱えるミクシィは、魅力的な候補のひとつでした。
現在、おもに携わっているのは、国内と繁体字版の「モンスト」のサーバーサイドの開発と運用です。事業部内の役割はフラットになっていて、誰々は◯◯担当というように決まっているのではなく、チーム全体で、「モンスト」の新規機能の開発、運用の改善、不具合の修正などにあたっています。また、大規模なトラフィックが来たときにサーバーの台数を増やしたり、緊急の障害対応をしたりすることもあります。
――1日のお仕事の流れを教えてください。
浅野
-
「モンスト」は、バージョンアップをおよそ月に1回のペースで実施しています。そのために必要な、「ゲーム内の新規機能の開発」に一番時間を割いています。そのタスクをこなした上で、サーバーコードの改善と運用に関わるタスクを行う日々です。
もちろん、プランナーとの打ち合わせや、クライアントエンジニアとのミーティングにも参加して、開発内容のすり合わせも行っています。
――「モンスト」は巨大なスマホゲームですが、サーバー周りはどのくらいの人数で担当しているのでしょうか?
浅野
-
サーバーサイドを担当しているのは、私を含めて15名のエンジニアです。このメンバーで数千台のサーバーを運用しています。
「モンスト」は特殊な(サーバー)環境で、弊社のデータセンターにあるオンプレミスに加え、Google CloudとAmazon Web Services、IBM Cloudという4ヵ所のサーバーを使っています。1つのサービス(スマホゲーム)を4つのサーバーを使って運用している例はほとんどないと思いますので、技術的にもチャレンジしがいのある環境です。
――サーバーサイドはユーザーからは見えにくい部分ですが、どんなところに魅力を感じていますか?
浅野
-
「モンスト」は、国内最大規模のサービスですので、私が想定している数を超えたアクセスが来てしまうこともあります。そういう出来事があったとき、「次はその負荷に耐えうるコードを書く」という覚悟で仕事に向かうところでしょうか。
コードベースでもかなりの規模(行数)になっているのですが、膨大なコードの中から改善点をピックアップしていくことには、やりがいと同時に難しさを感じています。ゲーム内のある動作の処理に時間がかかっていてサーバーにも負荷がかかっていたものを、自分の書いたコードで高速化できたとき、そして、その状態が下がったグラフや数値で明確になったときはうれしかったですね。
プロジェクトの規模が大きくなると達成感は味わいにくくなるものですが、このときは「モンスト」のサーバーサイドエンジニアをやっていて良かったなと思いましたし、達成感を得られました。
また、自分の作った機能の感想をインターネットなどで見ると、「ユーザーに届いている」という実感が生まれます。歴史のある、ユーザーの多いタイトルであるからこそ新機能への反応も大きいので、そうした反応を実際に見られることは大きな喜びです。
チャレンジと信用を積み上げることで自身も成長していく
――長く続くタイトルならではの問題を感じることもありますか?
浅野
-
サーバーサイドで使用しているミドルウェアもすべてが最新ではありませんから、全体をアップデートするなどして、少しずつ最新のアーキテクチャ(システムやソフトウェアの基本設計や共通仕様)に近づけるようにしています。
レガシーなサーバーも存在していますが、それ自体には元々「動いていた実績」があります。そのことを活かしながら、リファクタリング(コードの設計や構造を見直してプログラムを書き換える)や改善を図ることが私たちの仕事です。そのときは、「5年後に見た人が困らないコード」を書くように心掛けています。
先人の築いた資産を活かしながら、新しいことにチャレンジしていくことができるので、「レガシーなこと=悪いこと」ではありません。古いものを引きずっているわけでもなく、どんどんアップデートしていける環境はとてもおもしろいと思います。
――新しい技術の導入なども積極的に行っているのでしょうか?
浅野
-
「モンスト」は、オンプレミスのサーバーやクラウドなどを併用してきましたが、最近は「コンテナ」という仮想化技術も本番環境に投入しています。その結果、社内で使うツールなどの導入障壁も下がりました。
新技術をサービスの中や周辺(開発環境)に取り入れられるようになったことで、今まで以上に情報のキャッチアップをするようになりました。さらに、それぞれが見つけた新情報を社内のチャンネルで「共有して議論する」という、好循環も生まれています。
仮に、現在の運用状況にフィットしない内容であっても、何かしらのメリットを感じることができたのであれば、自身の責任で試すことができます。そうした新しいことや技術への挑戦をNGとする職場ではありません。
――自身のエンジニアとしての能力も伸びていると感じますか?
浅野
-
サーバーチームは、プロフェッショナルの集まりです。その一員として、コードをレビューしたり、自分の書いたコードをレビューしてもらえたりすることは、技術的に得るものがとても大きいですね。
「質の高いコードを書くメンバーがそろっている」場所で働けることは、一人のエンジニアとしてありがたい環境であると思います。
――1人の仕事人として成長を感じる場面もありましたか?
浅野
-
「素直であれ」ということを教わりました。障害の対応などの際に戸惑いを感じたり、ほかのことでもミスをしてしまったりするケースもあります。そういう場面では、「隠さず認める」ことが大切です。包み隠さず話すことで、メンバーの信用を得ることができます。信用があるからこそ仕事を任されますし、何か新しいことにチャレンジしたいときにやらせてもらえます。
具体例を挙げますと、サーバーサイドエンジニアのチームには、深夜の障害などに対応する2人1組の当番制が敷かれています。これはゲームにも大きな影響を与える作業ですが、その当番に、私は入社して10ヵ月目くらいに選出してもらうことができました。
与えられた仕事にしっかり応えるだけでなく、独自にツールを作成する「挑戦する姿勢」を認めてもらえたこと。その結果、メンバーに「この人になら深夜の障害対応を任せられる」と信用してもらえたことが大きかったと思います。作ったツールも内容を認められて、実際の運用に取り入れてもらいましたし、これも私を信用してくれていなければ実現しなかったことです。
ミクシィや「モンスト」が好きな人ほどフィットする環境

――ミクシィに入社して良かったと感じたエピソードを教えてください。
浅野
-
とにかく、コミュニケーションが活発です。部署が違っていてもつながりはできていて、エンジニア間の技術的な情報交換が行える「風通しのいい」環境が整っています。
会社で顔を合わせたことのない人でも、ちょっと技術的な話をすると、「実はオンラインでよく情報交換をしていた相手だった」ということも多いです。また、業務で困っている人がいたときはほかの部署でも助けますし、助けてもらえます。
――どんな人がミクシィに向いていると考えていますか?
浅野
-
ミクシィには、「ミクシィのプロダクトが好き」で入社した人が多いと思います。ユーザーがそのままチームに加わっているので、スマホゲームやサービスに対する理解度も高いです。
「モンスト」は、プレーヤー間のコミュニケーションを大切にしていますが、社員はコミュニケーションツールとして使っています。日常で遊んでいる「大好きなゲームをより良くしよう」という意識を、強く持っているメンバーが多いです。
これから入社を考える人についても、「モンスト」をはじめとするミクシィのプロダクトが好きであるほどマッチしやすいと思います。
――エンジニアも、そのプロダクトを好きなことが大切なのですね。
浅野
-
そうですね。でも、プランナーに言われたことをそのまま実装するだけでなく、ユーザー視点に立って考えられることも大切です。その要素を本当に喜んでもらえるのか、一人のユーザーとして違うと思ったらきちんと伝える。そのためには、プロダクトをしっかり楽しんでいる必要があります。
その上で、当然、エンジニアとしての視点も忘れてはいけません。技術的に問題があるようなら、それをしっかり伝えるようにしています。
――最後に、これからチームに加わる人に一言お願いします。
浅野
-
プロフェッショナルとして、より良いサービスをいっしょに作っていく日が来ることを楽しみにしています!
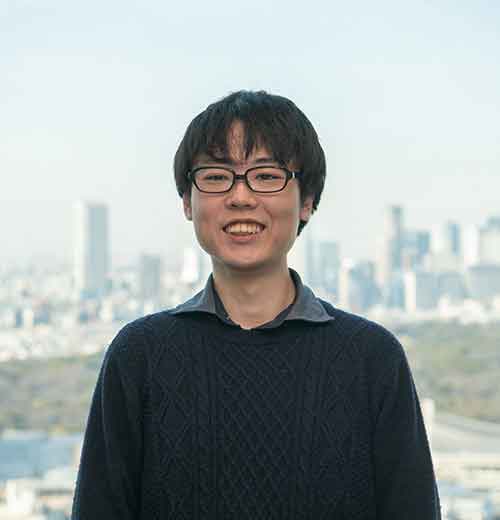
-
株式会社ミクシィ
モンスト事業本部 ゲーム運営部 モンストサーバグループ サーバ2チーム 浅野 大我 - 新卒でミクシィに入社。サーバーサイドエンジニアとして、世界でも有数のスマホゲーム「モンスト」の円滑な運用を支えている。
ミクシィ新規3Dタイトル・リードエンジニアインタビュー
SNSやスポーツ、メディアなど、多角的な事業を展開しているミクシィ。中でも、デジタルエンターテインメント事業では、「モンスト」に続くタイトル創出に力を入れています。
大手企業で世界中に多くのファンを抱えるタイトルに携わり、スマホゲームの開発経験も豊富な川端恭広氏が率いる新規プロジェクトもそのひとつ。立ち上げたばかりのチームの様子に加え、ミクシィならではのゲームづくりと、新メンバーに求めることなどを伺いました。
コンシューマーゲーム開発から、主流となるスマホゲーム開発へキャリアチェンジ
――初めに、ゲーム業界に入ったきっかけを教えてください。
川端
-
当時PCゲームは技術力が必要だったので、「PCのゲームを作りたい!」と思って勉強をしていました。ただ、就職を考えた頃はコンシューマーゲーム全盛期で、コンシューマーゲーム開発の方に進みました。この時代の変化は、ゲームの主役がコンシューマーからスマートフォン(モバイル)へと移るときとよく似ていたと思います。

写真:株式会社ミクシィ 川端 恭広さん
――作りたい気持ちとは別に、次に来るものが見えていたということでしょうか?
川端
-
コンシューマーゲームの開発をしていたときにも、「何か新しいことをやりたい」という思いがありました。そこで起業を考えたのですが、あまりうまくいきそうになかったこともあり、もう一度企業で働くことにしました。2010年頃の話です。コンシューマー系の企業が苦戦していて、モバイル系の企業もまだガラケー用のタイトルを作っている状況でした。
私は、スマートフォン用のゲームが伸びると考えていましたので、そのタイミングで(主流だった)ガラケーではなく(新興の)スマートフォンに向けたタイトルを開発している企業に移ることを決めたんです。次の時代の主役に早く関わったほうが、「未来が見える可能性が高い」という判断もありました。
――ミクシィに入社した経緯とミクシィに感じた印象を教えてください。
川端
-
転職を考えていた時期に、エージェントから「モンスト」に携わる仕事を紹介されたことをきっかけに選考を受けました。最終的に「モンスト」ではない新しいタイトルを作るポジションへのオファーを受け、今に至ります。
ミクシィは、とにかく「優しい人が多い」です。また、会社として挑戦することを推奨しています。結果、失敗であったとしても…もちろん失敗するつもりはありませんが、「チャレンジしやすい環境」はありがたいですね。
一方で、「ゲームづくりのノウハウが少ない」という印象も受けました。その部分を補完する意味でも、私の経験が活かせると思っています。ちなみに、入社したときは現在のプロジェクトはまだスタートしておらず、いくつか新しいゲームの企画を立ち上げようとしている段階でした。その中のひとつが、現在担当している「新規3Dゲーム」です。
現在開発中のタイトルは“3DのPvPアクションゲーム”
――新規タイトルの開発をしているチームの規模感について教えてください。
川端
-
エンジニア6名、アート(デザイン)に関わる者が9名、プランナーが2名というチームで作っており、私は企画の補佐を担う役割をしています。(※)
メンバーは中途採用が多く、コンシューマーの経験が豊富な者もいれば、スマートフォンをメインにしてきた者も、両方に携わってきた者もおります。いいゲームを作れる体制が整っていると思いますし、これから加わる人にもぜひ活躍してほしいです。※ 2021年インタビュー当時のチーム構成
――ゲームやチームをゼロから立ち上げる楽しさは、どんなところにありますか?
川端
-
スタートしたばかりということもあり、まだ着地点の見えないプロジェクトになっています。チーム自体も体系立てられた組織というよりは、企画の内容について毎日話し合っているような段階です。
そのような状況ですので、まずは「新しいものを作る」チームが、円滑に回るように支えていくことを第一に考えています。
――開発中のタイトルは、どんなゲームになるのでしょうか?
川端
-
スマートフォンで遊ぶタイトルですから「手軽であること」に気を配っていますし、何より「いかに楽しんでもらえるか」を重視しています。ユーザーに「価値ある時間を過ごしてもらえる」ことを目指しているというのが正しいかもしれません。
具体的な内容はまだこれから…という部分が大きいのですが、プレーヤー同士がバトルするPvPのアクションゲームになります。
他社とは異なるミクシィならではのゲーム開発環境とは
――多角的に事業展開しているミクシィですが、ゲームづくりにも影響はありますか?
川端
-
ミクシィはSNS等を運営してきた実績があるので、「サーバーに強い」ことは、ネットワークが必須である現代のゲームにおいて、大きなアドバンテージになります。また、スマホゲームの市場において強い(売上上位にある)会社であることは、ユーザーから信頼という点においてポイントとなります。
――ほかのゲーム会社と異なるミクシィならではの仕組みがあれば教えてください。
川端
-
上司との1on1が、週に1回以上組まれていることは特徴的ですね。時間は30分程ですが、チーム内のコミュニケーションをとても重視しています。
プロジェクトがもう少し進んでチームの規模が大きくなったタイミングでは、私も各メンバーとの1on1を組んでいけるようにしたいと考えています。
――どんな人が、ミクシィや現在のプロジェクトにマッチしますか?
川端
-
いろいろなことが「決まっているようで決まっていない」会社ですから、ゲームに限らず手探りで作ることを楽しめる人に向いていると思います。ルールがないからこそ「積極的に動くマインド」は大切ですし、そうしたチャレンジを会社として支援する姿勢はありますので。
私のプロジェクトで申し上げますと、スキルとして求めたいのはネットワーク系の経験です。特に、PvPのアクションゲームや、リアルタイムのアクションゲームの開発に携わった人を求めています。通信時のラグの調整、描画周りの問題を解決できる人に加わってほしい。開発に使っているツールはUnityなので、その知識がある人が望ましいです。また、サーバー周りの人材も足りていないので、ぜひ参加してほしいですね。

――新規開発チームのエンジニア採用において重視するポイントは何でしょうか?
川端
-
新規タイトルの開発環境は、基本的にはクラウドになりますので、クラウド環境でのサーバー開発・運用経験があることが望ましいですね。最低限のスキルがあることは当然として、何よりも重視しているのは「ゲームづくりが好き」なことです。また、「理解力」も必要です。1を聞いて10わかる人はめったにいませんが、少なくとも「相手が何を求めているのかがわかる」ことは大切です。
エンジニアに限らず、クリエイターは誰もが自分がやりたいことを持っていて、それを実現する技術もあるわけですが、それだけではチームとして成り立ちません。チームが向かう方向に合わせて、自身の役割を考える。指示を待つのではなく、自分から積極的に動く。そういう姿勢を持っていることが大事だと思います。
――スキル面以外で、求められる経験や考え方などがあれば教えてください。
川端
-
メンバーとしてではなく、リーダーとしてゲームづくりに関わった経験があるといいですね。ただ、リーダーの経験が長すぎると、今回のプロジェクトでは、進め方などでうまくいかない場面が出てきてしまう可能性があります。リーダーとして働いた経験を活かしつつ、新しいチームのメンバーと上手にやっていける、「柔軟な考え方ができる」人が望ましいです。
――最後に、応募を考えている人へメッセージをお願いします。
川端
-
「新しいゲームを世の中に出していきたい」という、意欲のある人と仕事をしたいと思っています。ゲームづくりをいっしょに楽しんでくれる人のご応募をお待ちしています!

-
株式会社ミクシィ
モンスト事業本部 MSスピンオフゲーム事業部 シードプログラムグループ シードAチーム 川端 恭広 - 誰もが知る某シリーズをはじめ、数多くのコンシューマータイトルの開発に携わった後、モバイルゲームの開発を経てミクシィに入社。「モンスト」シリーズのスピンオフタイトルでリードエンジニアを務める。