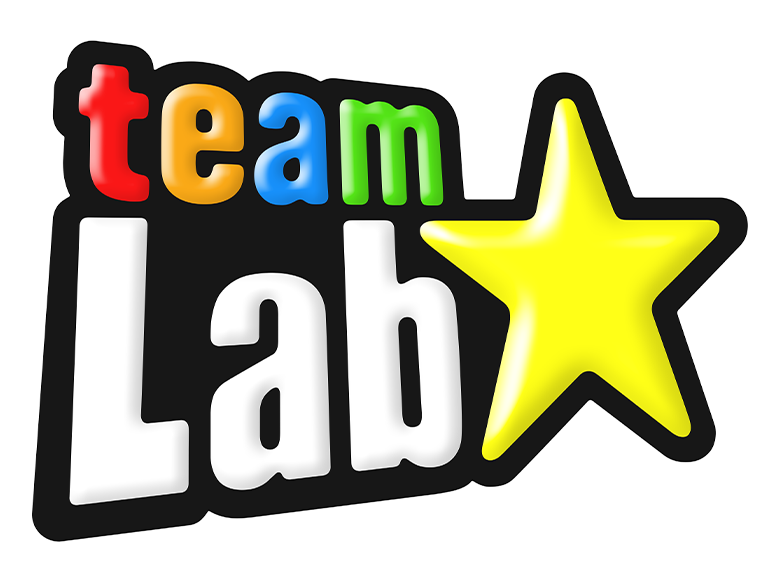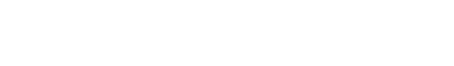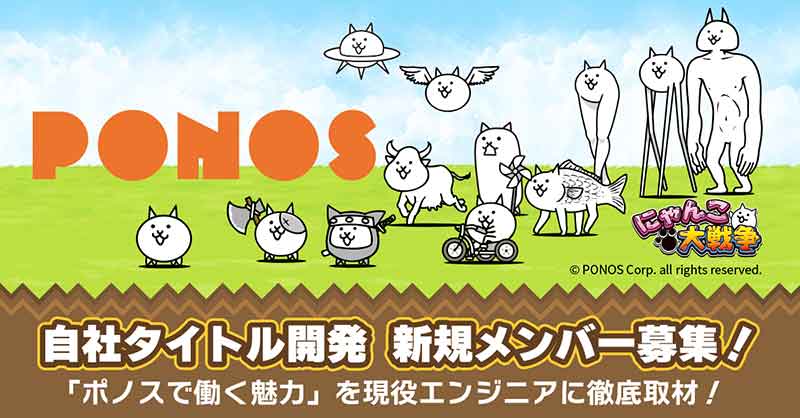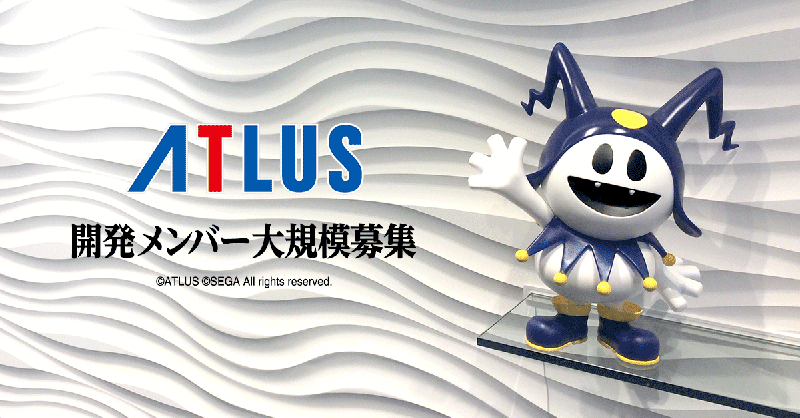チームラボ クリエイターインタビュー
デジタルテクノロジーによるアートで世界をリードするチームラボ。独創的なインタラクティブアートを制作するチームラボでは、ゲーム会社や映像制作会社出身のクリエイターが多く活躍しています。
今回はインタラクティブチームに所属するエンジニアと、コンピューターグラフィックスチームの3DCGアニメーターにチームラボの働き方や仕事のやりがいについて話を伺いました。

反応はダイレクト!チームラボのエンジニアは希有な体験
「現場の反応を肌で感じられることが一番」というインタラクティブチーム(※)に所属する
3名のエンジニアに、チームラボで働く意義や楽しさを聞きました。
(※)「森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボボーダレス」や「チームラボプラネッツ TOKYO DMM」での展示作品のような、リアルタイムでインタラクティブに動くアート作品やデジタルコンテンツを制作しており、企画 / デザインの段階からミーティングに参加し、開発を行います。
ふれた人の印象に残る作品を作る

写真:チームラボ株式会社 松田さん
――初めに、皆様がどういうきっかけで、チームラボで働くことになったのかを教えてください。
松田
前職はゲーム会社でスマートフォンのソーシャルゲームを開発していたのですが、少し仕事に疲れていたときに、たまたまチームラボの展示と出合いました。そのとき、子供たちがとても楽しそうに遊んでいまして、私も「子供が楽しめる作品を作りたい」と思ったのがきっかけです。スマホアプリは、どちらかというと大人向けでしたから。
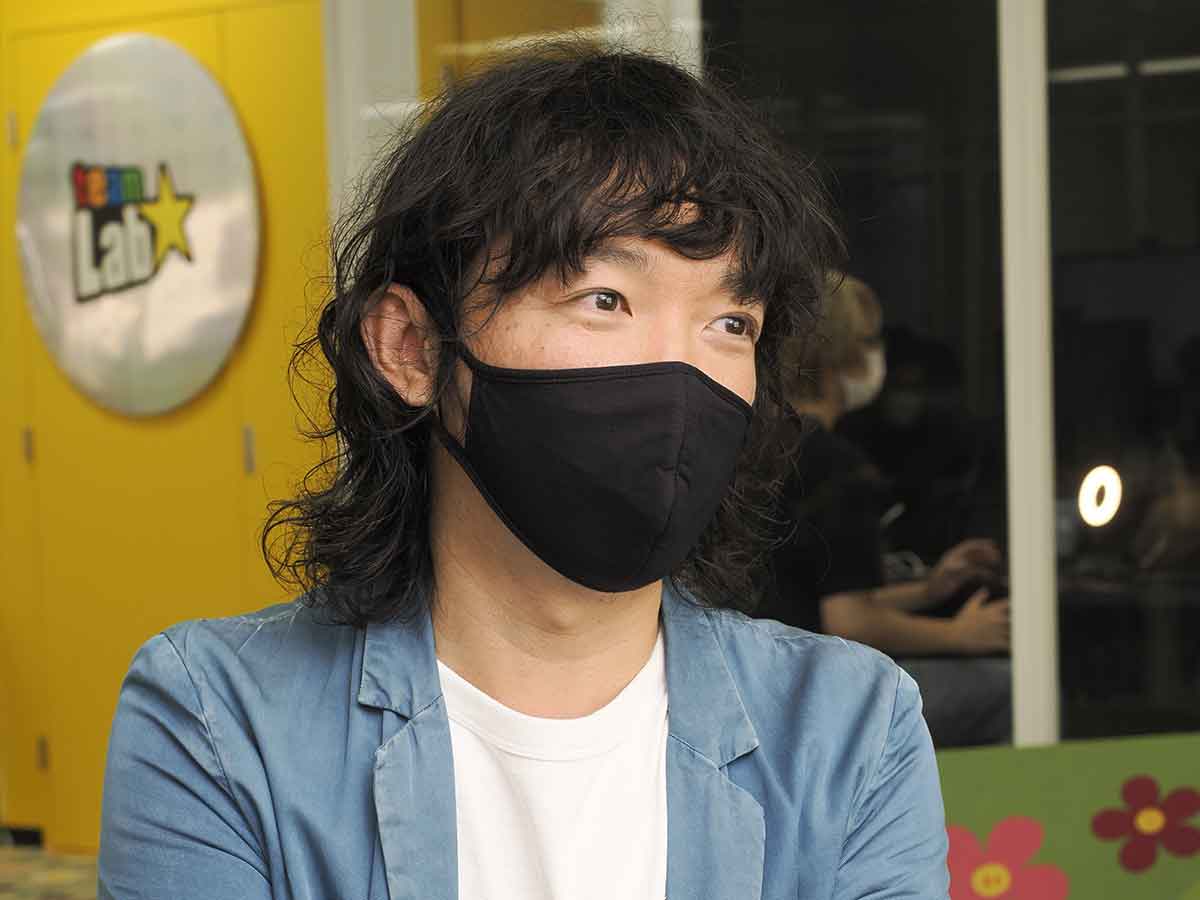
写真:チームラボ株式会社 迫田さん
迫田
私もゲーム会社でプログラミングをしておりました。元々チームラボが好きだったので展示はよく見ていたのですが、作品を体験している鑑賞者を直接感じられる、楽しんでいる瞬間を作り手が見られることに憧れを感じていました。当時作っていた家庭用ゲームの場合、ゲームショウ以外ではユーザーとほとんどふれる機会がありませんでしたので。
福永
私もゲーム会社に勤めていました。2年くらいは携帯のソーシャルゲームの開発もしましたが、基本的にずっと家庭用ゲーム機でいろいろなパートを担当させてもらい、多くの経験を積ませてもらいました。
ゲームよりもう少しフットワークの軽いものに携わりたい、見聞を広めたいという思いで転職を考えていたとき、転職エージェントからチームラボを紹介されました。

写真:チームラボ株式会社 福永さん
――数あるチームラボの作品の中で入る前から印象に残っているものはありますか?
迫田
「追われるカラス、追うカラスも追われるカラス、そして分割された視点」がすごく格好良かったです。
福永
インタラクティブチームの開発ではないですが「チームラボハンガー」です。お店(のラック)にあるハンガーを取ると、ディスプレイに服の紹介が出てくるプロダクトで、ソフトウェアの会社っぽそうなのにハードウェアもありなんだ、と領域の広さが気になりました。
――チームラボであることがわかる人にしかわからない時代の作品ですね。
福永
さりげなくお店に置いてありましたね。(笑)今も皆さんに気づかれないけど、チームラボのプロダクトはさまざまなシーンで見ることができます。例えば、「デジタルインフォメーションウォール」という巨大なデジタルサイネージは、商業施設のフロア案内や、美術館や博物館の収蔵作品を見せるデジタルギャラリー等に使われています。JR東日本の駅構内に設置されている「イノベーション自販機」はスマートフォンアプリ「acure pass(アキュアパス)」で購入した商品を駅の自販機で受け取れるのですが、こちらはチームラボのソリューションチームが開発しました。
――チームラボのエンジニアの働き方を、皆様のお仕事と合わせて教えてください。
松田
まず、「こういう作品を作りたいけどできますか?」という提案がカタリスト(※)からあります。自分から手を挙げるか、アサイン担当から声がかかったら、内容をよく聞いた上でシステム設計を行い、3Dモデルやテクスチャーといった素材をもらって取り込んでいきます。
それらをどう動かし、どう見せるか。インタラクションの部分をどうするかを考えることもエンジニアの範疇です。見た目だけでなく、細かく調整していくことになります。(※)アート展示における作品制作の進行管理、展示プランニング、現場設営業務を担当するポジションです。
迫田
既存作の拡張版のような作品では、必要な機能を追加するだけのこともありますが、基本的に全部ゼロからシステムを構築します。アイデアをどう実現するかは、エンジニアにかかっているわけです。
福永
あまりに突飛で無茶なアイデアの場合、それを実現できない理由をそれぞれのチームに説明して代替案を出すこともあります。とはいえ、実際に作れないものというのは、会場の制約や表現に対する制限が原因なことがほとんどです。
松田
いずれの場合も、仕様書はほぼ存在しません。作品によって完成イメージ図くらいはありますが、それすらない状態から始まることも多いです。
迫田
猪子(チームラボ代表 猪子寿之氏)を含め、話し合いをしながら作っていきます。システムができたらレビューをして、修正を加え、さらに意見を求める。どんどんブラッシュアップしていくサイクルを回しています。
福永
プログラムを担当する者、センサー周りの担当、作品の絵(アセット)や映像を作る者、音に携わる者。これらをカタリストがハブになってつなぎながら作品を作っています。そのプロダクトにメインで携わるプログラマーは、少人数です。
迫田
情報はGoogleドキュメントで蓄積していますし、GitHubにもアップしているので、そのエンジニアに何かあったときや問題が発生したときは、別のエンジニアが対応できるようになっています。また、同時に複数の箇所で展示があったときは一人ではフォローしきれないので、プロダクトの保守を複数のエンジニアに分散している場合もあります。
福永
自分の裁量が大きいと同時に、各専門職の仲間とみんなで作っている感じがとても楽しいです。また、作品を作っているときに「これは今後別の作品でも使えそう」という機能が出てきたら、パッケージ化して社内で公開しておくようなこともしています。本来の業務はもちろんこなしますが、このようなプラスアルファの作業も自由に行えますので、ノウハウの積み上げが作品や組織を横断して活きてくることも多いです。
松田
新規のプロダクトですと作り上げることが大変なこともありますが、以前の作品から引き継いだものや、ある程度慣れた作品に携わっていると余裕ができますので、横展開を考える機会も増えます。
チームラボのエンジニア全般にいえることですが、「役に立ちそうなことをどんどんやるぞ!」という気風がありますね。
ゲーム制作の経験はアートでも活きる
――開発に使っているツールは何ですか?
福永
インタラクティブチームのエンジニアはUnityや、その他いくつかのツールを組み合わせて使用しています。ちなみに、エンジニアの採用では、Unityを使える・使えないということよりも、「Unity”も”触ったら使えそうな下地があること」をチェックしています。
――ゲーム制作の経験は、デジタルテクノロジーによるアート作品の制作でも役立っていますか?
松田
一人でゲームを作るときも、あらゆる知識を総動員しますが、それに近い感覚です。これまでのゲーム制作での経験は、ほぼすべて役に立っていますね。
福永
それこそ、Unityのような便利なツールがない頃からゲームを作ってきました。今ならツールのボタン一発でできてしまうことでも「内部ではどういう処理をしているのか」を理解できていることは大きいです。
ゲームづくりとは違う部分もあります。スマートフォンや家庭用ゲーム機はハードウェアのスペックが制限になってしまいますが、私たちは要求に応じたスペックのPCを選定して開発や展示ができます。制作を進めていてハード的に困ったら、ハイスペックのPCを買ってくれば解決できることは大きいです。
松田
スマートフォンならディスプレイ、家庭用ゲーム機ならテレビ画面ですが、チームラボの場合は空間全体を作る点も大きく違います。でかい壁にドンと映す、あるいは施設自体を造ってしまう。自分が作ったものが大きく表示されることは、ゲームでは味わえなかった感動がありました。
――チームラボで働いている方の特徴や、働いていて良かったことを教えてください。
福永
さまざまなスキルを持った人達といっしょに仕事ができることは魅力です。マシンラーニングや音楽の専門家はもちろん、芸術に深く関わっている人と同じ座組みで制作を進めることは本当に楽しいです。
また、労働時間はチーム単位や人単位で決めています。「みんな自由にやっていいけど、やることはちゃんとやろう」というのが、チームラボの文化なのだと思います。また、開発機材への投資に理解があるので、予算のことを言われることなく必要な機材を買えることも大きいですね。
迫田
代表や役員に直接要望を伝えられる風通しの良さもあります。機材の話でいうと、「こういうグラフィックボードが必要」と相談をすると、それがチャットで送った相談でもすぐに承認してくれます。そもそも、上下関係や役職がありませんから、代表と役員がいて、ほかに役職名はないけどまとめ役(リーダー)がいるくらい。政治的な根回しや稟議といったことを、気にしながら働かなくていいことはありがたいです。
福永
影響範囲の大きいことはリーダーを通したほうがいいし、そのほうがみんな困らないけど、少人数で完結するようなことはいちいち通さずに進めても問題にはなりませんし、みんなすごく仲良く仕事ができています。
任されて自由にできる分、積極性は求められます。どんどん手を挙げて発言していくことが大切ですね。
――これまでのお仕事の中で、特に印象に残っている作品は何ですか?
松田
シンガポールのマリーナベイ・サンズの「デジタルライトキャンバス」です。大きなショッピングモールのスケートリンクの床を全面LEDディスプレイにリニューアルし、空中に光のシリンダー(直径7m・高さ14m)を新たに設置して、それらを全部キャンバスにしたプロジェクトで、私は床の部分の確認を担当していました。
その確認作業をスケートリンクの真ん中でポツンと行うものですから、ショッピングモールのお客様にものすごく見られる。そんな環境で作業をできたことは貴重な体験でした。
――エンジニアはリモートでなく、現地で調整するものなのですか?
松田
そうですね。やはり実物を見なければスケール感や色味がわかりませんので。
迫田
屋内・屋外を問わず、世界各地の現場で作業をすることになります。そして、私が一番印象に残っているのは、2018年にパリのラ・ヴィレット公園で行った「Au-delà des limites」です。のちにお台場で開催した「チームラボボーダレス」の少し前に開催した展覧会で、2作品程担当していたのですが、チームラボボーダレスのもとになるものができた瞬間があり、全体を見ても作品が別々でなくひとつにつながった非常に良い世界観になりました。
――これまでのお仕事の中で、特に印象に残っている作品は何ですか?
福永
私は「追われるカラス、追うカラスも追われるカラス、超越する空間」ですね。元々あった作品のインタラクティブ版を作ることになり、四角形の会場のすべての壁と床を投影面にしてカラスの世界にしたいというプロジェクトでした。映像をどうにかしてつなげないといけないというところから始まって、パースがついた奥行きのある作品になり、結果としてさまざまな会場で展示してもらえる作品になりました。
――チームラボの作品は世界で展開されていますが、制作する上で心掛けていることはありますか?
松田
もちろん、各地の展示にリアクションがあることはうれしいことですが、みんなに喜ばれるものを作ろうという意識はあまりありません。それよりも「自分たちがいいと思うものを作ろう」ということです。
迫田
地域によってクライアントの要望も様々あるのですが、それを入れたときに作品として成り立つかどうかが大切なので、作品の世界が壊れないかを気をつけながら相談して制作を進めています。
チームラボは社内もボーダレス
――さきほど、代表や役員とそれ以外という組織であるというお話がありましたが、どのようなキャリアプランをお考えですか?
松田
チームラボは、さまざまな分野の専門職の人が集まっており、それぞれが専門性を伸ばしていっているので、チームラボ内での役職でキャリアを築いていこうと意識している人はあまりいないと思います。
福永
普通の会社であればポジションという椅子があり、そこに誰が座るかというものがありますが、ここでは自分が椅子を持ってきて好きな所に座る感じです。とにかく「表現者志向」の人が多い。
メンバーが増え、プロジェクトの規模が大きくなってきたので、ツールなど制作環境を整えないと対応できない場面も出てきました。作品を作る上であると便利な機能、社内システムにあったほうが便利な機能を作る。いわば裏方的な、みんなを支える役割を担う働き方もできると思います。

――新しくインタラクティブチームに加わるエンジニアに求めることはありますか?
松田
受け身ではなく能動的に動ける人です。仕事で言われたものを作るだけではなく、趣味で作品を作って技術的なことを追求しているなど、勉強をしている人はどんどん成長していきますから。
実際、インタラクティブチームにはそういうエンジニアが多く所属しているので、そういう人のほうが本人も幸せでしょうし、チームにとってもいいと思います。
福永
チームラボを知ってる人が少し増えてきたためか、優秀な人材の応募が増えています。もちろん、特定の分野ですごい実績を積んでいる人も大事ですが、いろいろなことを経験してきた“いぶし銀”のような人が来てくれるとうれしいですね。
プロジェクトの規模が大きくなり、どんどん大掛かりになっていく中、作品制作以外の、いろいろなところで積まれた経験が活きてくると思います。
――最後に、応募者へのメッセージをお願いします。
松田
出張でいろいろな所に行って、自分が作ったものをユーザーが体験している姿が見られます。
迫田
PCの中で作ったものが世界に出て行きます。ここまで規模の大きいプロジェクトを作る経験は、なかなかできないものです。
福永
世界各地に出張はありますが、チームラボには英語ができる者が多数いますので外国語はできなくてもなんとかなります。興味を持った方はぜひ応募してください。

- チームラボ株式会社 松田勇磨
- スマホアプリなどの制作会社を経てチームラボに参加。インタラクションシステム設計とシェーダーを用いたグラフィック開発を担当する。これまでに担当した主な作品は「地形の記憶」「Strokes of Life」など。

- チームラボ株式会社 迫田吉昭
- ゲーム開発会社からチームラボのエンジニアに転職。グラフィックプログラミングとシステム開発を担当している。これまでに担当した主な作品は「世界は暗闇から生まれるが、それでもやさしくうつくしい」「秩序がなくともピースは成り立つ」など。

- チームラボ株式会社 福永秀和
- 数多くの家庭用ゲーム機のタイトルに携わったのち、チームラボに参加。インタラクティブアートの開発のほか、内製ライブラリやツールも開発。主な担当作品は「追われるカラス、追うカラスも追われるカラス、超越する空間」「The Way of the Sea」など。
チームラボの3DCGアニメーターの仕事
コンピューターグラフィックスチームに所属する3DCGアニメーターの2名に、日本だけにとどまらず、
世界を相手に作品を制作する魅力や、働き方について聞きました。
大規模かつインタラクティブな作品に携われることが魅力

写真:チームラボ株式会社 小宮さん
――まず、お二人の現在のお仕事を教えてください。
小宮
コンピューターグラフィックスチームで、3DCGアニメーターを務めています。肩書はアニメーターですが、アニメーションばかり作っているというわけではありません。
小林
同じく、コンピューターグラフィックスチームで、主にVFXを担当しています。現在の主な担当作品は「人々のための岩に憑依する滝」です。
――永遠に眺めていられる滝ですよね。お二人はチームラボに中途で入られたと伺っていますが、前職はどんなお仕事だったのでしょうか?
小宮
いろいろと経験してきました。企業のPVやCMなど、実写系のコンテンツを制作するスタジオから、アニメーションのスタジオに移って撮影…つまりコンポジットを担当しました。それから、実写の撮影アシスタントをしていたときもありましたが、基本的にはずっとCGを作っています。
小林
私は2020年の秋に転職してきたので、チームラボで働いて2年になります。それまでは、CG制作のプロダクションでエフェクトアニメーターをしていました。そこから別の会社に移り、映画やCMで使うVFXの制作、モーションキャプチャーやディレクションを担当していました。VFXは水や炎、爆発のエフェクトが得意です。
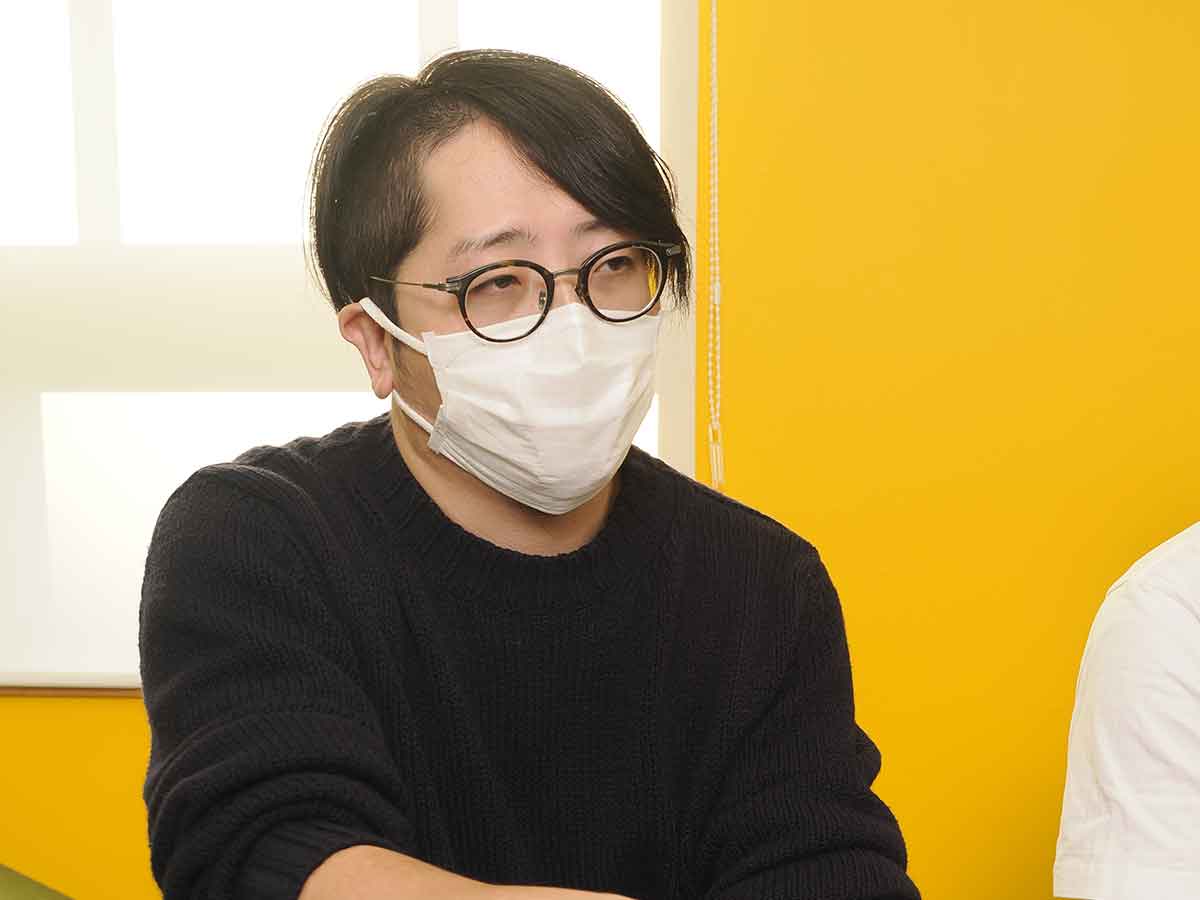
写真:チームラボ株式会社 小林さん
――転職先としてチームラボを意識したきっかけは何ですか?
小宮
趣味でVJをやっていたので、元々プロジェクション系に興味がありました。2010年頃からプロジェクションマッピングが話題に上るようになって、チームラボの名前もよく聞くようになったのでチェックはしていたんです。その後、前職を辞めたタイミングで、もうちょっと深く調べてみたら、プロダクト やウェブ の仕事もしていて、おもしろいなと思って。
小林
知人に、お台場にあった「森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボボーダレス」を案内してもらったのですが、そのときに「なんじゃこれは!」という衝撃を受けたのが最初の出会いで、子供たちがすごく楽しそうに遊んでいる姿に魅力を感じました。ちょうど(水などを表現する)流体系のスキルがマッチしました。
小宮
ここまで大規模でインタラクティブなプロジェクトを動かしている組織は、日本ではほかになかったです。でも、実は面接を受けた時点では、チームラボの作品を、そう意識して見たことはありませんでした。
小林
今はプロジェクションマッピングを手がける会社もできていますが、やはり規模が違うと思いました。チームラボが一番大きく、幅広く、いろいろなプロジェクトを世界中でやっていると思いますね。
――お仕事ではどんなツールを使っているのでしょうか?
小林
現在担当しているプロジェクトではSideFX社のHoudini(フーディーニ)を使って流体の表現を模索しています。日々、試行錯誤しながらアップデートを繰り返していまして、「ちょっとだけこうしたい」という部分をうまくコントロールできるのが魅力というか、仕事をしていて楽しい部分です。
小宮
私は、2024年に竣工予定の「teamLab Phenomena Abu Dhabi」に携わっていますが、こちらでは3ds MaxとUnreal Engineを使用しています。ちなみに、Unreal Engineを使うのは、私も今回のプロジェクトが初めてです。
――これまでのご経験は、現在のプロジェクトに活きていますか?
小林
一連の仕事を、一人で一通りできるように育ってきたことは大きいです。そのベースがあるので、今の仕事では「いかに効率良くできるか」というところに頭が働くようになっています。
また、チームラボ内で「こういうものがあったらいいな」という話を聞いたときに、パッとツールを作って「どうですか?」と提案することもできます。もちろん、ツールを作ること自体好きということもありますが、これまでの制作経験があってのものだと思いますね。
小宮
これまでの経験が活きているという意味においては、私もやはり最初から最後まで制作の手順を踏んできたことは良かったです。どのポジションを与えられてもこなせるのは、すべてのプロセスを経験してきたからこそだと思っています。
――仕様書が存在しないプロジェクトが多いそうですね。
小林
基本的に仕様書がないものばかりです。「作りながらみんなで考えていこう」というスタイルは、ほかのスタジオと大きく違うところかもしれません。
小宮
一般的なクライアントワークであれば、初めにクライアントからの要望やイメージボードがあって、フローもしっかりしていることが多いと思います。でも、アート作品の場合は、誰も正解がわかりませんから、いろいろな人が意見を出しながら作り上げていく。途中まで作ったものが猪子(チームラボ代表 猪子寿之氏)のレビューを受けて方向性が変わったりもします。
でも、ウォーターフォールではなくアジャイル的な作り方をしているので、スケジュール感も含めて臨機応変に対応できるのは強みですね。
小林
もちろん、クライアントがいることでピリッとするので良い刺激になりますが。一方、アート作品は日々アップデートを重ねてより良いものにする「ずっと続いていくもの」です。
――アート制作とクライアントワーク、ご自身が希望するプロジェクトに参加できるのでしょうか?
小宮
やりたいものがあるのであれば、望むプロジェクトに入れる可能性は高いと思います。
小林
自分から手を挙げてプロジェクトに参加することもあれば、「これを作れるなら、こっちもできるかな」という振られ方もあります。私は水を作ることが好きでしたので、言わば自動的に滝を作る役割を与えられたのかもしれませんが。
小宮
現在の私のプロジェクトの場合は、Unreal Engineを使って何かしようという空気感があって、ちょうどフィットしそうな話が来たというタイミングもありました。そして、初めに作ったプロトタイプがなかなか良い結果だったので、そのままUnreal Engineが採用されました。Unityにもいいところがたくさんありますし、チームラボとして使用ツールに制限は設けられていませんが、チームとしてチャレンジしてみようということです。
――使ったことのないツールに挑戦できる環境があるということでしょうか?
小宮
技術に対して貪欲な人は吸収も早いので、入ってからさわっても、すぐに戦力になってくれると思います。Unreal EngineやUnityの練度については、心配せずに応募してください。
――お二人がこれまでに関わったチームラボのアートで、特にお気に入りの作品は何でしょうか?
小宮
中部国際空港で行っていた「FLIGHT OF DREAMS」です。格納庫に置いてあるジャンボジェット機と館内空間をダイナミックに使用した映像と音のショーで、空間を演出するプロジェクトでした。あんなに間近でジャンボジェット機を見る機会はないので貴重な経験でした。
小林
私は、九州の御船山楽園で毎年夏から秋にかけて開催している「チームラボ かみさまがすまう森」です。建物や池にプロジェクションを施しました。空気が良い場所ですし、何より会場内にある御船山楽園ホテルのサウナがすごくいいので、サウナーの人はぜひ行ってほしいと思います。(笑)もうひとつ、「廃墟の湯屋にあるメガリス」も好きです。こちらも滝の作品(憑依する滝群)があります。
アートは公開後に手を加えて、どんどん良くできる
――チームラボでの作品づくりの魅力は、どんなところにありますか?
小宮
チームラボにはさまざまなジャンルの専門家がおり、彼らと作品を作れることは本当におもしろいと思います。建築家やビジュアルデザイナーというように、普段接する機会のないプロフェッショナルな人とともにひとつの作品を作り上げる。これは、ほかにはない魅力であると思います。
小林
リアルタイムレンダリングを担当しているインタラクティブチームと仕事をすることも多いのですが、エネルギーにあふれて頭の回転が速い彼らと切磋琢磨しながら作るところも楽しいですね。
ほかには、空間をつくるということもやりがいのひとつであると思います。テレビの画面に映すのではなく、たくさんのプロジェクターを置いて広くて大きな空間を作り上げる経験はなかなかできません。「ディティールにこだわって作り込む」「コンセプトを深掘りしていく」という、異なるアプローチができる点も魅力です。
小宮
あとはやはり、実際にお客様が作品をご覧になって、「良かった」という声を聞くと満たされます。
小宮
チームラボのアートはずっと更新していくことができます。作業として終わりがないのではなく、どんどん良くなっていくことが楽しい。アップデートしても、また違う部分に気づいてしまいアップデートする。この繰り返しで作品が良くなっていきます。

――チームラボに入って良かったことを教えてください。
小宮
自分たちが企画したものを、チームラボとして自分たちのために作っていることがすごくいいと思います。
小林
同感です。もちろん、お客様も大事ですが、その前にチームラボとして自分たちで作りたいと思う作品を作れるのは大きいです。
――これからコンピューターグラフィックスチームに応募してくる人に求める能力はありますか?
小林
アートが好きで、チームラボの作品が好きな人でしょうか。そのことがベースにあった上で、技術を追求している人、どうすればゼロからイチを生み出すことができるかという思考ができる人は重宝されると思います。
小宮
作品を最初から作り上げた経験のある人です。「卒業制作でこの部分を担当した」という経験も大事ですが、たとえ30秒の映像であっても、自分で企画を立ち上げてやり切った経験があることは大きいと思います。
小林
それから、何かひとつ「自分の武器がある人」がいいですね。
小宮
ある程度自分のスケジュールを個人個人で設定・管理して進めていく方針なので、「タスクを自己管理できる人」のほうがいいかもしれません。
――最後に、これから応募してくる人へメッセージをお願いします。
小林
私はここに刺激を求めて入りましたが、新たな刺激を求めている人にとって最高の環境が整っていると思います。新しいことにチャレンジしたい。アートが好きで、チームラボの作品に携わりたいと考えている人の応募をお待ちしております!
小宮
「アートに興味のある人が多い」という印象があるかもしれませんが、実際はみんな様々な業界からいろんな人が集まっているので、その点は心配しなくて大丈夫です。私もチームラボに入ることが決まったとき、妻に「そんな格好で出社して大丈夫?」と心配されましたが、そんな心配は無用でした。
実際は、自分の意見をしっかり持っている人が多いので、ご自身のやりたいことをはっきり出せる人には良い組織だと思います。ご応募お待ちしております!

- チームラボ株式会社 小宮智彦
- 映像制作会社、アニメーション制作会社、フリーランスでの活動を経て、2017年11月にチームラボに参加。コンピューターグラフィックスチームに所属し、現在は2024年公開予定のプロジェクトに携わっている。

- チームラボ株式会社 小林太郎
- 都内のVFXプロダクションで映画やCMのVFXやCGを担当後、チームラボに参加。コンピューターグラフィックスチームで「LUXE」の空間演出を行ったほか、Houdiniのツール開発や「滝」のシミュレーションなどで幅広く活躍中。