ゲームのプラットフォームといえば、ハードウェアを指すことが一般的です。1990年代中盤、 家庭用ゲーム機で覇権を争っていた任天堂とソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE/当時はソニー・コンピュータエンタテインメント)、 セガの3社が発売していた「NINTENDO64」「PlayStation」「セガサターン」がプラットフォームと呼ばれています。
3社間で行われた競争を、ユーザーは「どのハード=プラットフォームを選ぶか」「遊べるゲームの種類」という視点で見ていました。 一方、デベロッパーの立場からすると、「どのプラットフォームで自社のタイトルを出すと売れるか」「どのハードが市場を押さえるか」が大きな問題でした。
家庭用ゲーム機の種類=プラットフォームという考え方は現在も続いており、先行する任天堂の「Nintendo Switch」を、 いずれも2020年に発売されたSIEの「PlayStation 5」とマイクロソフトの「Xbox Series X」が追いかける展開となっています。
なお、かつては家庭用ゲーム機(携帯型ゲーム機を含む)とPC(Windows/Mac)がゲームのプラットフォームでしたが、 2020年現在、Appleの「iOS」とGoogleの「Android」、つまりスマートフォンが世界最大のプラットフォームとなっています。
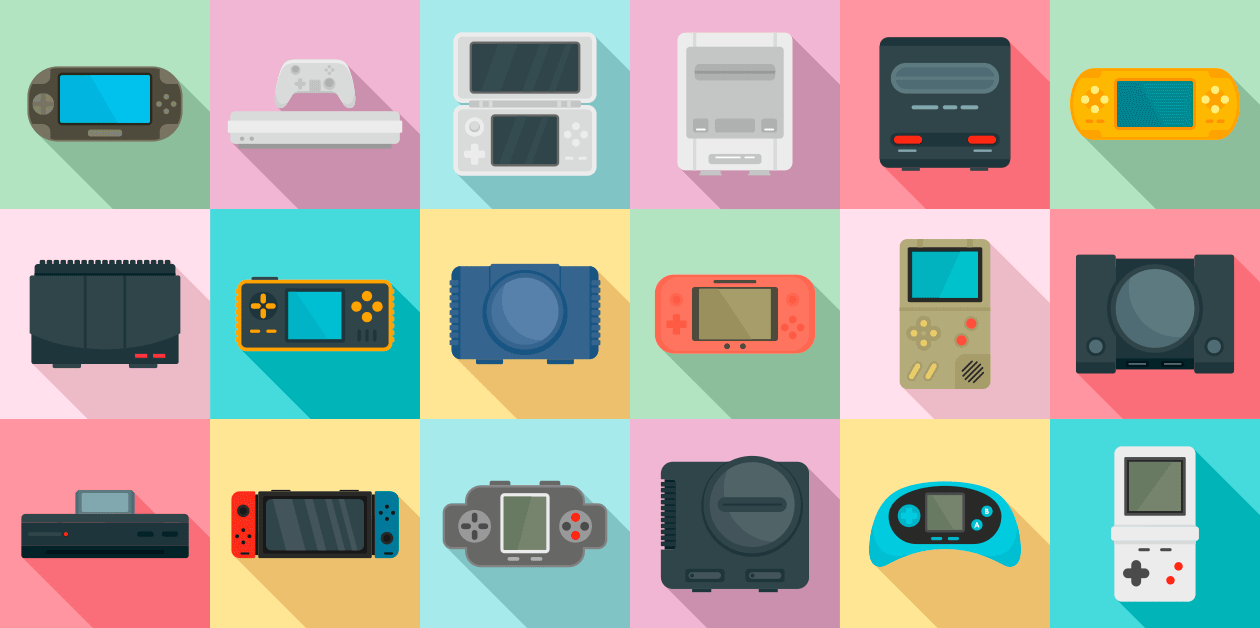
家庭用ゲーム機やスマートフォン、PCは今なおプラットフォームとして存在し、それぞれ巨大な市場を形成しています。 しかし、デベロッパーにとっては、ハードウェア、もしくはOSの供給元の方針や時代の趨勢に、多大な影響を受けることが大きな問題です。
家庭用ゲーム機でいえばハードウェア(本体)の普及台数=ゲームの最大販売数ですから、開発を始める段階で「ゲームリリース時の本体の販売状況」を予測しなければなりません。 一方、スマートフォンの場合、もはや1人1台持っていることが当たり前という状況のため、本体の母数はさほど考えなくても大丈夫ですが、随時行われるOSの更新、 機種による性能差などへの対応を行う(アップデートし続ける)必要があります。つまり、これら従来のプラットフォームでゲームを提供する場合、 ハードメーカーとOSの供給元の方向を見ながら制作・販売することが求められるのです。
こうした問題をクリアするために、海外のデベロッパーはハードウェアやOSに頼らない独自のプラットフォームを志向するようになります。 初めに大きな成功を収めたのは、1997年「ディアブロ」のサービスインと同時に開設されたBlizzardの「Battle.net」です。 その後、「スタークラフト」「ウォークラフト」シリーズといったメガヒットタイトルが生まれたことで、PCにおけるオンライン対戦のプラットフォームとして揺るぎない地位を確立。 2020年現在も「デスティニー2」「オーバーウォッチ」などのメジャータイトルを抱え、eスポーツのプラットフォームとしても世界をリードしています。
Battle.netに次いで登場したのが、「ハーフライフ」「レフト フォー デッド」シリーズなどで知られるValve社が提供した「Steam」でした。 2002年のGDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)で発表され、2004年には超大作「ハーフライフ2」のSteam上でのダウンロード販売に踏み切ります。 その後、Electronic ArtsやTHQといった欧米の大手パブリッシャーのほか、カプコンやスクウェア・エニックス、コーエーテクモゲームスなど日本の大手パブリッシャーもゲームの提供を開始。 当初はPC(Windows)のみだったプレイ環境も、MacOSやiOS、Androidから家庭用ゲーム機まで、幅広くフォロー。ワールドワイドの同時接続数も2,000万人を超え、 インディーゲームも含め、数万タイトルを超えるゲームが遊べる巨大プラットフォームとなっています。
Battle.netとSteamの大成功を受け、欧米の大手パブリッシャーは独自のクラウドプラットフォームを展開していきます。 有名なところでは、Electronic Artsの「Origin」、Ubisoftの「Ubisoft Club」、Epic Gamesの「Epic Games Store」などが挙げられるでしょう。
いずれも、プラットフォームを運営するパブリッシャーのヒットシリーズをプレイできることが目玉になっています。 Originでは「エーペックス」「バトルフィールド」「FIFA(フィファ)」などのシリーズを、Ubisoft Clubは「レインボーシックス シージ」「アサシン クリード」「ファークライ」、 Epic Games Storeなら「フォートナイト」といった具合です。どの作品も家庭用ゲーム機などへの提供も行われ、 ハードウェアの垣根を越えてネットワーク対戦ができるようになっていることも特徴です。
さらに、Googleの「Google Stadia」やAmazonの「Amazon Luna」もサービスを開始しています。2020年12月の段階では、先行するSteamなどを脅かす存在ではありませんが、 日米欧の大手パブリッシャーがゲームを提供しており、両社の影響力を考えると無視できないプラットフォームになりそうです。
家庭用ゲーム機のようにメディアを生産する必要もなく、自社でサーバーなどを用意せず、純粋にゲームを提供すれば完結するクラウドプラットフォームは、
デベロッパーやインディーゲームメーカー、個人クリエイターにとって低リスクでチャレンジできる場所になっています。
アイディア勝負のカジュアルゲームから重厚長大なAAAタイトルまでが同居しており、ユーザーの範囲が広いことも魅力です。
ユーザーの評価はダイレクトかつリアルタイムに拡散しやすく、内容次第では(ローカライズなしで)世界と戦えることも見逃せません。
クラウドプラットフォームは、ゲーム単体のダウンロード販売ではなく、サブスクリプションモデルも増えています。
代表的なサービスは、Microsoftの「Xbox Game Pass」、Appleの「Apple Arcade」、Electronic Artsの「EA Play」など。
いずれも、安価で大量のゲームが遊び放題であることを目玉にしており、既存のクラウドプラットフォームとどう棲み分けるのかが注目されます。
ユーザー自身がゲームをプレイするのではなく、ほかの人が遊んでいる様子を楽しむゲーム配信サービスも、プラットフォームといえるでしょう。 専用のソフトウェアも充実しており、デベロッパーにとっては広報の場や、新たな収益の可能性がある場として機能しつつあります。
ゲーム実況という言葉が生まれた「YouTube」や「ニコニコ動画」だけでなく、Amazonが運営しeスポーツとの親和性が高い「Twitch」、 世界的なSNSである「Twitter」アカウントがあれば簡単に配信できる「ツイキャス」、スマートフォン専用の「Mirrativ」など、多くのサービスがしのぎを削っています。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!
お問い合わせフォーム
PICKUP求人